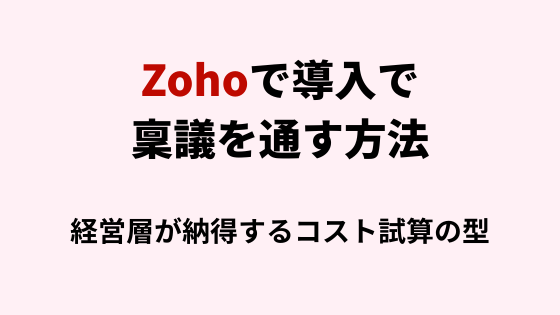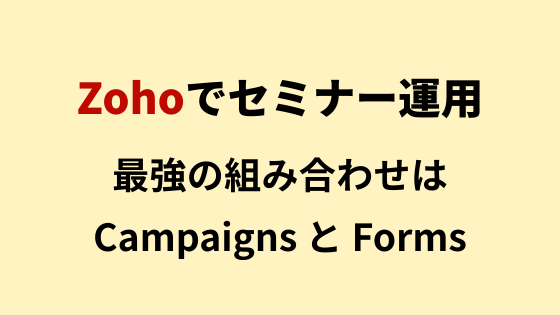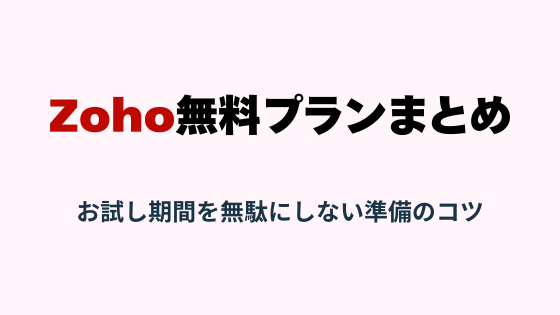Zohoは「低コストで必要十分な機能がそろっている」とよく言われます。
しかし、実際に導入を検討している担当者にとっての本当の壁は「社内稟議をどう通すか」。
経営層や上司は「コスパが良い」と言われても、感覚的なメリットだけでは動きません。
必要なのは 数字で納得させる材料 です。
本記事では、稟議で問われやすい観点を整理しつつ、実際に使える「コスト試算の型」を紹介します。
この記事をベースに自社の数字を当てはめれば、そのまま提案資料に活用できます。
第1章:稟議で問われる代表的なポイント
Zohoに限らず、新しいSaaSを導入するときに稟議でチェックされやすい観点は大きく次の4つです。
1. 現在の運用コストはいくらか
- CRM、メール配信、フォーム、ストレージなど、ツールごとの契約費用
- 社員が行っている手作業(CSV加工・リスト整備など)の工数コスト
→ 稟議では「現状コストの全体像」が前提になります。
2. Zoho導入後、どの程度コストが下がるか
- 各サービスをZohoで置き換えた場合の月額費用
- 無料枠やバンドルされている機能をどう活用できるか
→ 数字で「△△円削減」と示すことで説得力が増します。
3. 導入までの学習コストはどれくらいか
- 社員がZohoを使いこなすまでに必要な学習時間
- 研修やトライアルの工数を「初期コスト」として見込む
→ 削減額だけでなく「回収時期」を示すために必要な観点です。
4. 既存サービスからの移行コストとリスク
- データ移行にかかる作業時間や並行稼働の期間
- 移行時のトラブルリスク(データ欠損、ユーザー慣れ)
→ 「リスクを承知の上でどう対応するか」を事前に整理しておくと、承認がスムーズになります。
第2章:コスト試算の型とタイムテーブル
コスト試算の型(サンプル)
| 項目 | 現状 | Zoho導入後 | 差分 |
|---|---|---|---|
| CRM | 50,000円/月 | 0円(無料3ユーザー枠) | -50,000円 |
| メール配信 | 30,000円/月 | 10,000円/月 | -20,000円 |
| CSV加工工数 | 60,000円/月 | 15,000円/月 | -45,000円 |
| 合計 | 140,000円/月 | 25,000円/月 | -115,000円/月 |
👉 この試算だと、初期の学習・移行コストを含めても 半年以内に投資回収 が可能、というイメージを示せます。

上記はあくまでも例なので、あなたの会社の現状と、運用にマッチするプランで比較してくださいね。
導入タイムテーブル(例)
| フェーズ | 期間 | 主な作業 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 無料で試す | 0〜1か月 | 無料プランで基本機能を検証 | 小規模チームでトライアル |
| 契約する | 1か月目 | 有料プラン契約・管理者決定 | 契約条件とアカウント整理 |
| 運用に合わせて型を整える | 1〜2か月 | タブ・フィールドのカスタマイズ | 最小限の構成に絞る |
| コンバートする | 2〜3か月 | 既存サービスからデータ移行 | 並行稼働でリスク回避 |
| オンボーディングする | 3か月目 | 社員への説明会・研修 | FAQ・マニュアルを整備 |
| 実運用 | 4か月目〜 | 全社展開・定着化 | 定期レビューと改善 |
👉 この「コスト削減シミュレーション」と「導入スケジュール」をセットで見せると、
経営層も「いつ投資回収できるか」がイメージできて承認が通りやすくなります。



こちらはあくまでも一例です。導入するプランや規模、実現したいことによって、それぞれ必要な期間は変わってきます。
第3章:稟議でよく突っ込まれる質問と回答例
Zoho導入の稟議で上層部からよく出る質問を整理しました。ここでは代表的なものを取り上げ、回答の方向性を示します。詳細は必要に応じて別記事(セキュリティ・BCP)を参照してください。
Q1. 「セキュリティは大丈夫なのか?」
想定される突っ込み
- 海外サービスだから不安
- 個人情報を扱って問題ないのか
回答の方向性
- Zohoは世界で8,000万人以上が利用している実績がある
- ISO27001/27017/27018認証取得済み
- 日本国内はAWS東京リージョンを利用


Q2. 「災害や障害に強いのか?」
想定される突っ込み
- 地震や災害があったらデータはどうなる?
- バックアップや冗長化は?
回答の方向性
- データは冗長化され、定期バックアップも実施
- 世界的に複数のデータセンターでフェイルオーバーが可能
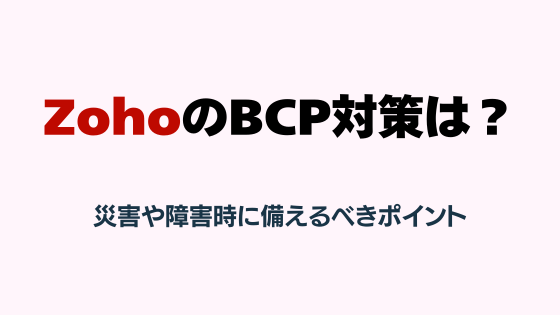
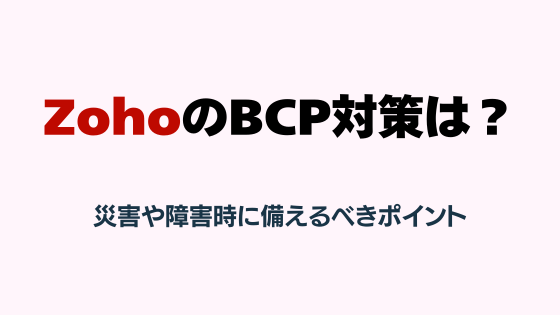
Q3. 「なぜZohoなのか?SalesforceやHubSpotじゃないのか?」
想定される突っ込み
- 有名ベンダーの方が安心では?
- Zohoにする理由は?
回答の方向性
- SalesforceやHubSpotと同等の主要機能を、数分の一のコストで提供
- 小規模〜中規模企業向けに「ちょうどいい機能量」
- 日本語サポートやパートナーも拡大中
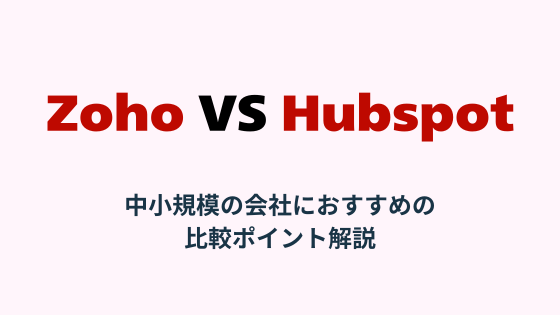
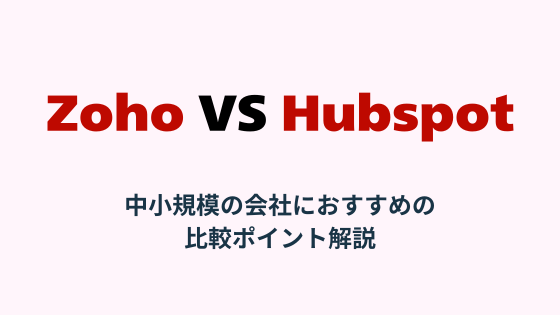
Q4. 「誰が運用するの?定着できるの?」
想定される突っ込み
- 情シスがいないとうまく回らないのでは?
- 運用が属人化しないか?
回答の方向性
- 管理者向けマニュアル・研修を準備
- 無料トライアルで“型”を整えてから全社展開すればリスクが少ない
- Zohoはカスタマイズが簡単なので、システム担当がいなくても調整可能
Q5. 「移行リスクはないのか?」
想定される突っ込み
- データ移行でトラブルが出ないか?
- 既存システムとの二重管理にならないか?
回答の方向性
- CSV形式でのインポート・エクスポートに対応
- 移行は段階的に行い、数か月は並行稼働するのが一般的
- 最小単位から移行することでリスクを抑えられる
第4章:提案書にまとめるコツ
ここまで整理した「コスト試算」と「導入タイムテーブル」、そして「想定質問と回答例」を、そのまま提案書に落とし込めば稟議はかなり通しやすくなります。
特に意識したいポイントは以下の4つです。
- 現状コストを数字で示す
- 月額・年間ベースで「今いくら払っているのか」を明確に。
- 導入後の削減額を具体的に示す
- 「月△△円削減 → 年間□□万円」など、経営層が一目で分かる形に。
- 回収までの期間を出す
- 「初期コストを含めても半年以内に回収可能」と示せば承認が得やすい。
- 移行リスクと対策をセットで提示する
- 「並行稼働」「小規模チームから導入」「バックアップ」など、リスクを軽減するプランを添える。
👉 この4点を押さえておけば、「コスト削減は分かったけどリスクが心配」という反論にも落ち着いて対応できます。
まとめ
Zohoはコストパフォーマンスに優れたSaaSですが、導入担当者が直面する本当の課題は「稟議をどう通すか」です。経営層や上司を動かすには、機能の多さや安さを強調するだけでは不十分で、数字に基づいた説得力が必要になります。
具体的には、まず現在の運用コストを整理し、Zohoを導入した場合にどの程度の削減が見込めるかを示すこと。そして、導入時に発生する学習や移行のコストを加えたうえで、どのくらいの期間で投資を回収できるのかを明確にすることが大切です。さらに、移行リスクや並行稼働の必要性についても触れておくと、経営層の不安を払拭できます。
本記事で紹介した「コスト試算の型」と「導入タイムテーブル」を活用すれば、短時間で説得力のある提案資料を整えることができます。稟議に必要な要素を数字で整理し、シンプルかつ現実的に示すことが、Zoho導入を実現するための一歩となるでしょう。
💡 Zohoの無料お試しを始める前に…
👉 無料お試しを無駄にしないコツはこちら
※当サイトはZoho公式ブログではありません。リンク先には広告が含まれています。